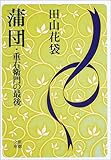【 本 】明治のツンデレ、竹中時雄、このゲスい感じ、嫌いじゃないです-『蒲団・重右衛門の最後』
渠(かれ)は名を竹中時雄と謂った。
奥さんには三人目の子供ができ、新婚のときめきって何? 食べられるもの? という今日このごろ、みなさまにおかれましていかがお過ごしでしょうか、竹中時雄ですという話。
彼、竹中時雄は仕事にも身が入らないし、同じことを繰り返す毎日の生活にも飽き飽き。家を引っ越しても、友人と遊んでも、趣味に打ち込んでみても、どれもこれもつまらない。四季の移り変わりを眺めていても、出るのはため息ばかり。どこの乙女やねん! そのうち、息をするのもめんどくせー、となりそうですね。
そんな彼が結局何をしたいかといえば、
道を歩いて常に見る若い美しい女、出来るならば新しい恋を為たいと痛切に思った。
要するに、新しい恋がしたい、新しい彼女が欲しいと。
前置きが長いわりに、欲望はストレート。
男のそんな身も蓋もない生理を一生懸命分析して、一般化します。
三十四五、実際この頃には誰にでもある煩悶で、この年頃に賤しい女に戯るるものの多いのも、畢竟その淋しさを医(いや)す為である。世間に妻を離縁するものもこの年頃に多い。
毎朝の出勤ですれ違う女教師を見るにつけ、妄想はとどまることを知りません。
恋に落ち、待合茶屋でエッチして、たまにデートして、奥さんが難産で死んだら、彼女を新たに後妻に迎えて……、いやあ、ローリングソバットを延髄に叩き込みたくなってきますね。
古女房にはもうときめきなんかないなあ、やっぱ人生は萌えだよ、萌え、燃え! どこかに可愛い女の子、いねえかなあ。明治時代のことですから、三十四五というと結婚十年目くらいでしょうか。うーん、見事な中年クライシス。
そんな暗い情熱を燃やす時雄のもとに、あるとき神戸女学院の生徒から手紙が届きます。実は、この竹中時雄は「竹中古城」というペンネームで物語を書く小説家でした。彼の書く作品にすっかり心酔している横山芳子ちゃんは、ぜひ先生に弟子入りして、文学を一生の仕事にしたいとのこと。
われらが竹中センセイ、渡りに船かと思いきや、一度は彼女をたしなめる返事を書きます。女が文学に携わるものではない、母として生きよ、処女が文学をやるのは危険極まりない、なんて。でも、芳子ちゃんも負けません。是が非でも先生の弟子になりたいと思いの丈を綴り返してきます。
それで竹中センセイ、しぶしぶ弟子入りを認めます。しかし、その返事を書き送る際にも、芳子ちゃんに写真を要求しようとしたり、文学をこころざす女に美人なんておるまいとうそぶいてみたり、どこまでもゲスい。
ところが本人を前にして美人であることが分かると、すました顔の裏で大喜び。
ハイカラな新式な美しい女門下生が、先生! 先生! と世にも豪い人のように渇仰して来るのに胸を動かさずに誰がおられようか。
なに、このツンデレ。
自分の内面のことだけをひたすら綴る「私小説」という文体形式は日本独自のものだと言われます。その日本初のものとなったのが本作、田山花袋『蒲団』。
ひたすら、男の身勝手さを綴った文章を読んでいて、幾度「どこの読売小町だよ!」というツッコミを入れたことでしょう。
今日は冒頭だけご紹介しましたが、物語は、やがて芳子ちゃんに若い男の影がちらつき、先生がそれに嫉妬し、いよいよ昼ドラのような泥沼の展開になっていきます。先生の偽善者っぷり、ツンデレっぷり、ゲスっぷりの本領が発揮されるのもまだまだこれからです。
明治期に書かれた文学小説ですが、ここまでツッコミを入れながら読める作品というのも決して多くはありません。うえでは辛辣なことを書きましたが、わたしは決して嫌いじゃないです。こういう小説もありなんだなと、初めて読んだときは、目からウロコが落ちました。
ボリュームもそれほどありませんし、ストーリーも難解ではありません。一読してみると、ひとりひとり違った読み方もできるのではないでしょうか。普段、文学に縁のないかたにもオススメできる文学小説です♪